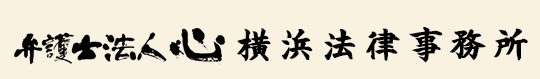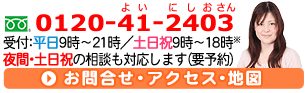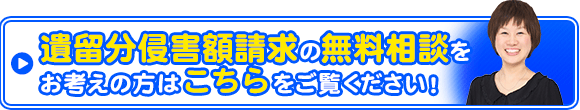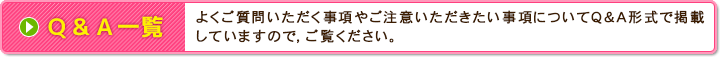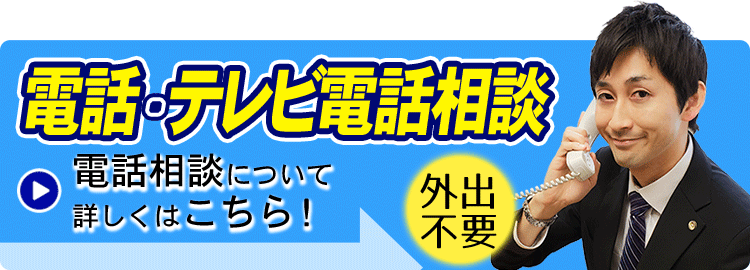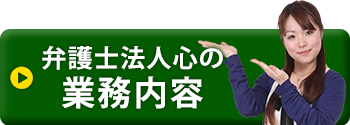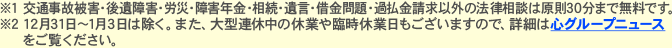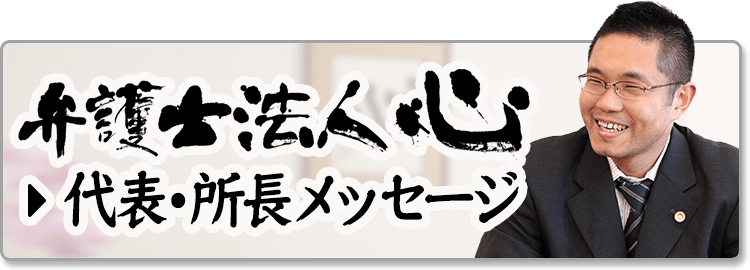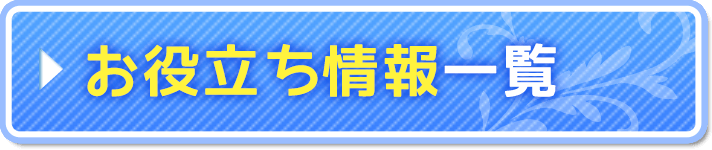特別受益と遺留分について
1 特別受益と遺留分の関係について
例えば、被相続人(遺産1000万円)の相続人に子A、子Bがいた場合に、被相続人が自身の遺産全てをAに相続させるという遺言書を書いていたとしましょう。
この時、被相続人の死亡直前に、被相続人が相続人の一人に対して900万円を贈与してしまった場合、実質的な遺産は100万円となってしまいますので、BはAに対して原則として100万円に対する遺留分25万円しか請求できないことになります。
しかし、本来、Bは250万円の遺留分を請求できていたはずなのに、生前に贈与しただけで遺留分を減額することができるとするのは不公平な結果をもたらすことになります。
そこで、法律上、共同相続人の内の一人に対してなされた贈与が①特別受益に該当し、②その贈与が相続開始前の10年以内に行われていた場合には、その贈与した財産を遺産に持ち戻すことができることとされています(民法1044条)。
今回は、このような特別受益と遺留分の関係性について解説していきたいと思います。
2 特別受益の要件について
上述のとおり、特別受益が遺留分の計算に含まれるようにするためには、生前贈与が特別受益に該当しなければなりません。
特別受益に該当するための要件としては、その贈与が
① 遺贈
② 婚姻のための贈与
③ 生計の資本としての贈与
に該当することが必要とされています(民法903条参照)。
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
「遺贈」とは、遺言書によって相続人に移転した相続財産のことを指し、原則として遺留分の計算に最初から含まれているため、今回は割愛いたします。
「婚姻・養子縁組のための贈与」は、典型的な例としては、持参金、支度金のほか、結納金等が挙げられます。
「生計の資本としての贈与」は受贈者(=贈与を受けた人)の生計の基盤となる財産上の給付を指すと考えられています。
例えば、居住宅地や住宅購入費の贈与、開業資金の贈与がこれに当たるとされています。
簡単に考えるのであれば、配偶者間、親族間の扶養義務の範囲を超えるような大きい金額の贈与については、「生計の資本としての贈与」として特別受益に該当すると考えられることが多いようです。
この「扶養義務の範囲を超えた」かという点について、月10万円を超えた部分について扶養義務を超えているとして特別受益性を認めた裁判例(東京家審平成21年1月30日)がありますので、10万円を超えているか否かは一種の判断要素になる可能性があります。
3 相続の開始前10年以内にされた贈与であること
特別受益は、被相続人の生前に行われた生前贈与であるため、生前贈与を受けた受贈者が不足の損害を被らないようにするため、原則として相続の開始前10年以内に限って遺留分の計算に含めることとされました。
もっとも、この制度を悪用されないように、10年以上前にされた生前贈与であっても、③贈与者及び受贈者が遺留分権利者を害することを知ってした生前贈与については、例外的に10年を超えて遺留分の計算に含める事ができる(1044条1項後段)とされています。
もっとも、被相続人の死亡前10年以上前から、遺留分の権利侵害を認識しつつ生前対策を行うことは難しいため、被相続人が経営していた会社の株式の贈与等の相当高額な贈与であり、それ以外に被相続人に財産と呼べるものが一切ない場合など、相当高いハードルが求められる規定となります。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。